・発表者:山本賀代(べてるしあわせ研究所・研究員)
・共同研究者:下野勉
月刊専門誌『精神看護』に連載中の「当事者研究」が評判です。
精神病を体験した人について、学者が「研究」するのではなく、ご本人が、自分自身と病気について「研究」するというのですから、前代未聞です。
なぜ引きこもるのか,なぜ爆発するのか,自分にとっての病気とは――
第7回のでは、社説・「べてるの風」に登場した下野勉さんの恋のその後が「研究対象」になりました。
とても普遍性のある「喧嘩のしかた」(o^^o)がテーマですので、筆者と医学書院のご承諾をえて転載させていただきました。
私たち(山本賀代:自己病名=依存系自分のコントロール障害、下野勉:自己病名=依存系爆発型分裂病)が、一緒に暮らしはじめたのは、2000年7月からである。浦河の町内に一軒家を借り受けて、“家族としての暖かく平和な家庭”を夢見ながらの生活がはじまった。私としては、生きていること自体が不安な毎日のなかで、そんな自分をまるで保護してもらうかのような感覚だった。彼は彼で「自分のコントロール障害」を抱えながら、そんな自分を棚上げして何とか私の面倒を見てやろうという気持ちが、がっちりと食い込んだ心理状態であった。しかも、すでにお互いに自分では背負いきれない「こころの爆薬」を抱えていた。だから、最初から無理な設定である。はじめから容量オーバー気味の状態でスタートした「新婚」生活だったが、最初は、酒に酔った勢いを借りての喧嘩が“順調に”始まった。
喧嘩が始まると最初はすぐ逃げていた。今度は、それが悪いといって喧嘩になる。私は私で、彼の昔付き合っていた女性のことを持ち出して攻撃に打って出る。最初のうちは、喧嘩しても仲直りができていた。しかし、回を重ねるにつれて、治まりきらない前の怒りに新たな怒りが重なり合い「発酵」し、更なる喧嘩のエネルギーが蓄積される。しかも、両者ともしだいに「どこを責めたら一番刺激的か」というコツがわかり喧嘩の腕が上達し、過激さを増すのである。
そのようななかで出会ったのがアメリカで出版された『Fighting Fair for Families』という英文の冊子であった。つまり、喧嘩にもルールがあるという主旨の本で、家族間暴力を防ぐための心理教育を目的にしたものである。これを読んで「喧嘩のメカニズム」が驚くほどわかった。そうであれば、あらためて自分たちの喧嘩を客観的に研究してみようということになった。それほど、自分たちの喧嘩は末期的で、藁にもすがる思いだったのである。
この研究の目指すものは、当たり前のことだが、何といっても「平和」を取り戻すことである。喧嘩に費やす時間、体力、費用、精神的なダメージは極めて大きい。お互いに仕事にも行けなくなる。近所の評判もがた落ちで、外を歩く時、被害妄想も増す。良いことは、山本にとって夜逃げが多くなるので、友達が増えることと、下野にとってはこういう厳しい時期に結構気合いの入った良い曲ができること(下野はギター弾きである)ぐらいである。
もう我慢できない。何とかしよう。そのような切羽詰まった状況が、冊子の翻訳のエネルギーとなり、研究の動機となった。
2人がそれぞれ個別に赤十字病院の医療相談室に出向き、ソーシャルワーカーとの間で「喧嘩」のメカニズムの解明と回復の方法を求めて自己研究を始めた。頻度としては、2週間に1度、1時間の時間をとり、「自分の気持ち」に焦点をあてた研究をした。特に、喧嘩の悪循環を見極め、今起きていること、今の気持ちを図に表し整理した。人間関係においては、家族における自分の役割や行動を思い出し、振り返りを行なった。
研究のポイントは、相手の問題ではなく、「自分」をテーマにすることであった。そして、まとめた研究の骨子をべてるしあわせ研究所チーム内で報告し、話し合った。先行研究である「爆発の研究」(2002年1月号掲載)も大変役に立った。
喧嘩のメカニズムを明らかにするという研究は、それ自体が、喧嘩のきっかけになるような気がして怖かった。カップル同士の喧嘩は、どこにでも起きていることである。しかし、他より目立つのは、①話し合いが全く成立しないこと、②自己に対する過剰な防衛――これ以上深く傷つきたくないからと先制攻撃をかけること、③両者が、常に疑心暗鬼で被害的な感情をもっていること、④ともに根底に寂しさを抱えていること、等である。
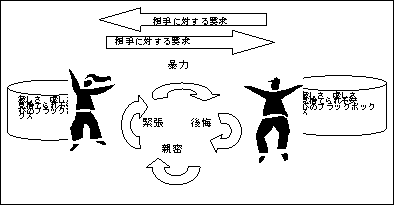
ともかく、2人の喧嘩の分析を続けるうちに見えてきたのは、喧嘩には「一貫性」と「法則性」が在ることである。特徴的なのは、自分が自分を分かっていないのに、相手には「判って欲しい」と求めることである。お互い元々が寂しい、虚しいという見捨てられ不安の上で生きてきた。だから、常に「相手が自分を見てくれているかどうか」が気になってしまう(図1)。そこで私は、自分の寂しさの源を辿ることから研究を始めた。
私は生まれてからの10年間を鹿児島で過ごした。父は医者、母は専業主婦。兄が2人と母方の祖父と祖母との7人家族だった。小学校の2年生で祖母の死に立ち会った。3年生のとき幼なじみが喘息で亡くなった。父の都合で4年生の時に関西に転校した。その年祖父も急死した。いつしか私は死の恐怖に漠然と怯え続け、いつも自分や家族の劇的な死の場面を空想しながら過ごした。兄たちも思春期を迎え、家族の関係は悪化した。父は毎日時間通りに帰宅し、晩酌をするのが日課だった。家族は父が戻ると緊張した。機嫌が悪いと父は酒を飲みながら家族に説教をした。私は「かわいくない」「お前が男だったらな」などの否定的なメッセージを受け取った。兄たちは私に比べて出来が悪いと言われ、母は育て方が甘いと言われていた。そんな父に、母も兄たちも反抗できなかった。いつしか私1人が家族の不満を父にぶつける役になっていた。私は学校でも家庭でも体を張って正義の味方役をした。
中学はイギリスの学校に1人で行った。はじめての寮生活、規則通りの行動を求められた。いじめもしたし、いじめられもした。そのうち夜毎に恐ろしい「猫のお化け」――今考えると、幻視の始まりだった――に脅かされるようになった。大人たちが敵に思えた。授業を受けるのが苦痛でなんとか妨害しようと1人で学級崩壊を始めた。普段掃除なんかしないのに、授業中に急に掃除を始めたり、隣りのクラスの授業妨害をした。他にも団体行動を乱す行動をとり続け、2年の秋に退学、日本に「強制送還」となった。
それから日本の公立中学に通ったが、1人浮いた存在で、相変わらず大人には敵意を示した。クラスの男子からいじめにもあった。高校では国際学校に入った。規則のない自由な校風になじむことができ、友達もできた。先生も人間なんだと思えた。ただ毎日の通学電車で痴漢にあっていた。その時点で私の自己評価は痴漢よりも低く、「この人は、会社での地位もあるだろうし、家には家族もいるだろう。私が我慢すればいいんだ。痴漢の対象にしか見えない私が悪いんだ」と思っていた。
英語が好きだった私は成績を伸ばし、大学に入ることができた。入学後すぐに男性と酒でトラブルを起こし、大学に通うのも苦痛で大学にいても空気が薄く感じられ、2か月で辞めた。アメリカの大学へ留学するのが夢だったが、自分の意思では決められなかった。数か月パチンコ屋でバイトした後、親の希望どおり京都の大学へと進学した。一人暮しを始めたが、ほとんど大学へは通えなかった。1年のうち冬の間半年をひきこもり、夏の間外に出ては酒、男性、暴力といった問題を起こし、また引きこもる生活をした。大学生活の後半は海外逃亡もした。ネパールの現地人の彼氏――彼はジャンキーで、私も一緒になって薬物にはまり遊び暮らした――をつくり結婚すると約束した。大学はなんとか卒業することができたが、父の大反対でネパールの彼とは別れた。
勿論就職もしなかった。疲れ果てた私に中学時代の友達から北海道の浦河に行くとの情報が入り、「北海道で静養したい」と思い浦河までついてきた。牧場でバイトをしながらのんびり暮らす予定だったが人間関係もこじれ、大学に入った頃からの睡眠障害もひどくなり幻覚に悩まされ、見かねた友人が浦河赤十字病院の精神科に連れて行ってくれた。そこでべてるの家の存在を知り、今の彼と出会ったのだった。
依存系で自己コントロール障害に苦労していた彼とは、すぐに息があった。彼は彼で、アルコール依存の猛烈サラリーマンの父親、姉2人の「父子家庭」育ちであった。7歳で母親をガンで失う体験もしている。2人とも、背中に寂しさという欲求不満の充満したタンクを背負い、しかし、決して「背中のタンク」を振り返ることなく生きてきた。
どういったきっかけで平凡な日常生活が刺激的な戦場へとなっていくのか。私1人では考えるきっかけさえつかめず、相手のせいにばかりしていた頃、「リスパダール事件」が起った。事件の数日後にソーシャルワーカーに手伝ってもらって、自分たちに何が起っていたのかを解明する作業をした。
事件当日、始まりはごく普通のありふれた朝だった。2人それぞれの仕事をこなし、帰宅後、ほとんど無言の緊迫した空気の中で夕食を済まし、怒りのキャッチボールは始まった。私が発したのが「死ね」。彼が「なんでお前なんかに…」、私「うるさい、死んでしまえ」、彼「出てけ」、私「出てくよ」、彼「お前なんて迷惑なだけだ、くそガキ」、私は酒を飲み始める。彼「寝るわ」とフテ寝。私は怒りに任せて酒を煽り、死んでやると思いその日まで飲まずに貯めておいたありったけのリスパダ-ル(推定30錠?)を飲み込み床についた。
次の日から丸三日、私は薬の副作用でレロレロになり体はガチガチで息をするのもやっとで、望みどおり「死ぬ思い」をした。表面上のあらすじはこういうわけだが、さらに掘り下げて普通の1日から「死ね」発言に至るまでの自分を振り返ってみた。その日、私は昼から作業所にいってパソコン関係の仕事を1人でした。この時点で私の中の「気持ちの子ども」が寂しさにグズリ始めたが、かまわず仕事を続けた。
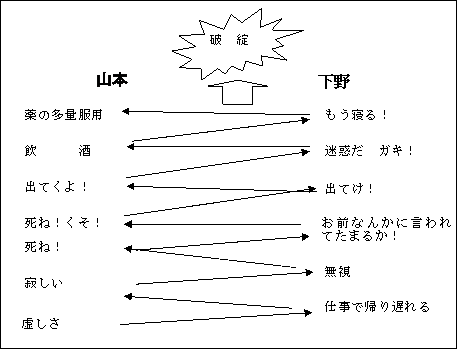
5時になって帰宅の際、知人に“にら”を頂く。私は寂しさと疲労でいっぱいになった気持ちの契機付けに、「よーし、今日はこれで餃子を作って彼と楽しく食事しよう!」と帰宅し、休むことなく買い物をした。ここからが魔の3時間である。私1人のなかで起こっていた葛藤を見てみよう。買い物最中も1人で餃子作りに励む間も、どうしようもない寂しさ、虚しさが込み上げてくる。自分では自分の気持ちの面倒がみられない。彼と話したい。慰めて誉めてもらいたい。彼に分かってもらいたい欲求が高まる。しかし彼はいつもの時間になっても戻らない。連絡もない。こんなに可哀相で惨めで健気な私を忘れて、彼は職場で仲間に囲まれ、いや女性に囲まれ楽しく笑っているに違いない。妄想は膨らむ。彼の楽しそうな声まで聞こえてくるようだ。私の疲れ、寂しさ、虚しさは、この間に彼に対する失望に変わり、怒りへと表情を変える。時計の針の音に合わせてカチカチと怒りが部屋中に満ちていった。夜8時、彼が帰ってくる。彼もそこに漂う空気で「やばい」と察知し「武装」する。そして普通の1日が悪夢へと変貌していくのだった(図2)。
しかしながら、決定的に2人でこの問題に真剣に取り組むきっかけとなったのは、2002年2月、厳寒の日の事件であった。翌朝講演に出かける彼に、私が言った「夕飯つくりたくない」という一言からだった。今思えば、彼がべてるの仲間と講演とギターの演奏に出かけてしまうことに、1人残される私は寂しさが募っていた。取り残される不安や、彼のギターの演奏と歌を聴くであろう多くの「女性」を意識してイライラしていた。それが、最初の一言になった。「また始まった…」と私の妨害を意識した彼は、自分の苛立ちを静めるためにウイスキーを飲みだした。そして、いつものように口論と暴力が始まった。「これはまずい」と思った私は、喧嘩から逃れるように仲間の家に非難した。
案の定、仲直りしようと言う彼からの電話があった。大丈夫と判断した私が甘かった。彼が仲直りにつくった鍋もの――今思えばあるもの全部を放り込んだ得体の知れない気持ちの悪い料理だった――を囲んで「仲直りしよう」という彼の提案に、「そんなのいやだ! じゃあ、なぜ殴ったの!」と詰問する私。その後は、予定通りの喧嘩の再開だった。彼は既に酔っている。口論が、「プロレス」に変わるのには、時間がかからなかった。反撃に転じた私は「酔っ払いは家にいて欲しくない!外で寝な!」といって彼の布団を玄関から外に放り投げた。すると彼は逆切れし、掴みかかって来たので外に逃げた。外に逃げた私に向かって今度は彼が、私の使っている布団や家財道具を外に放り出した。深夜の2時頃のことであった。携帯も壊され、病院のソーシャルワーカーに助けを求めるための作戦として、公衆電話から110番をしてパトカーを呼んだ。そして、警察署に連れて行ってもらい電話を借りてソーシャルワーカーに連絡をとった。「どうしよう」という私の問いかけに、ソーシャルワーカーの対応は、いつもの通りそっけないものであった。やむなく仲間の家に避難し朝を迎えた。家の周りは布団や家具が散乱し、見るも無残なありさまだった。
この出来事は、2人にとっても事態の深刻さを認識させ、研究を始める重要なきっかけとなった。そして出た結論が、「前向きな別居」であった。
「別居」は、今まで誰彼からとなくアドバイスされたことであった。「別居」とは、私たちにとっては失敗を意味し、挫折を重ねる恐怖が、それをためらわせてきた。だから、「同居」しながら、ありとあらゆる方法を試してみた。最初は「相手が変わればいい」と考えてみたり、次に「自分が変わればいい」と思い直したりいろいろやってみた。そして出た結論が、「自分達のやり方を諦めること」だった。諦めたら、「別居」も怖くなくなった。
表1のとおり、物理的に「別居」という形を取ったことによる効果は、てき面だった。
| 内容 | 別居前 | 別居後 |
|---|---|---|
| 掃除 | 物を壊しても掃除する気にもならない | 自分の責任なので掃除する |
| コミュニケーション | ぶつかるのが恐い。相手の行動にびくびくする。ぶつかると、酒、暴力、自傷行為に走る | ぶつかると自宅へ帰る。携帯で身の安全を確認。話し合わないという選択もできる |
| 攻撃性 | 暴力。関係が近すぎて、問題ではなく相手を攻撃する | 危ないと思ったら退却する |
| お金 | 山本が一括管理。そのため小さなことでも口論の種になる | それぞれが、自己管理。下野は金欠状態。 |
| 武器の使用 | すべての「武器」を使えるように鍛えられ、応用が自在になる | 「武器」を使用する前に家に帰る。相手を大事にしたいという気持ちがあることに気付く。 |
| 食事 | 山本が調理、家事担当で不満が蓄積 | 一緒に買い物、時々一緒に食事 |
| 仕事 | 休みがち。喧嘩にエネルギーの80%を注ぎ、残りで仕事 | 出勤できるようになる。仕事に50%のエネルギーを注ぎ、残りで余暇。喧嘩が無くなった。 |
| 友人関係 | 恐がって、誰も寄り付かない | いろいろな人が遊びにくる |
この激しかった2年間に渡る同居生活は、私のそれまでの破天荒な人生にとってある意味での新たなスタート地点となった。中学のころから問題児だった私は、これまでたくさんの失敗を繰り返しながらも、自分という人間に焦点があたらないように自分のことをできるだけ隠し、自分という人間から逃げるため、そして夢のような自分だけの救世主を求めてあちこち渡り歩いて、問題を起こしては居場所を失い人間関係を次々と切りながら生きてきた。
浦河に来てからも私は相変わらず問題を起こしたが、不思議とここではそのことによって自分を追い詰めなければならなくなるような空気がなく、かといって手厚く保護されるようなこともなかった。そして、ただその問題を私自身の課題として考え悩むための手助けをしてもらった。私の場合は、まず私という人間(感情を備えた人間として)の存在を認識することから始まった。自分の気持ちに気付き、それをもとに行動し、その責任をとり、適切な言葉で表現するということ。ごく当たり前のことのようだが何十年も自分をほったらかしにしてきた私にとっては、毎日の生活が練習、失敗の繰り返しだった。
今でもたまに思い出してはゾッとしたり悲しくなったりするようなこともある2年間だったが、今では胸を張って、あの生活が私には必要だったのだといえる。周りの人たちにもさんざん迷惑をかけた。あの時はごめんなさい。だけど、見守ってくれたこと、いちいち話しを聞いてくれたこと、夜中に押しかけても泊めてくれたこと、みんなの手助けがあって私はたくさん感じ、考え、とことんまで悩み、ついには諦め、新たな実験として次に進むことができたと感謝している。
あの生活で私の中のたくさんの自分に出会うことができた。仲間や専門家にたくさんの言葉をもらった。自分の弱さを出せたことで今までには無かった人とのつながりが持てるようになった。自分の苦手な部分を知り、自分にはまだまだ可能性があるということも分かった。一人暮しを始めて4か月。1人といっても「きれい荘」というアパートに女の子3人で暮らしている。週に1度は3人でミーティングを開き、近況報告をし、お茶を飲み話をする。彼のところへもほぼ毎日会いにいって一緒にご飯を食べたりしている。時折、無性に寂しくなるが、今1人で感じる寂しさは苦労の末に自分で選択した寂しさなのだからと、その質の高さを噛みしめている。2人で居てどうしても分かり合えない寂しさは1人の寂しさよりつらかったから。
こうして平和を手にしたかのように見える私だが、最近は不安発作にみまわれるようになった。生きている限り問題は尽きないようだし、自分という人間のメンテナンスは少しも気が抜けない。こんな私でもいつかは家族を持ちたいと夢見ている。人と人が2人で1人ではなく、1人と1人としてつながって生きていけるということを信じて、これからも自己研究を続けていくつもりだ。「今後の悩み深き私に乞うご期待!」と自分に言ってあげたい。
やまもと・かよ
中学~高校時代にかけて学級崩壊させていた経験を生かし、近隣の中学校の先生、PTA、生徒たちに向けて「学級崩壊させる生徒の気持ち」を講演することがある。
べてるの家の講演会では、下野勉さんのギターに合わせて歌っている。最近、歌集『べてるの家のパンチングローブ』を完成。一部300円にて販売中。「べてるの家に電話をしてくれた人に、お望みでしたら電話口で歌います(ただし、その場にいれば)」とのこと。
●べてるの家:〒057-0022 北海道浦河町昌平町東通34
※「当事者研究」の連載にに関心をもたれた方は医学書院(03-3817-5660)へ