※写真にマウスポインタをのせると説明が表示されます

『怪傑! ハウスハズバンド』という愉快なタイトルの本が世間をアッといわせたのは、1984年のことでした。
筆者は日本のライヴハウスの草分け、『ぐゎらん堂』を開いた村瀬春樹さん。
育児休業法も男女共同参画社会基本法もなかった時代のことです。「男性学のバイブル」「女性行政担当者の必読文献」といわれ20年間、ロングセラーを続けました。

月日は流れ、2006年1月。
『経産省の山田課長補佐、ただいま、育休中』が、世間をアッといわせることになりました。
筆者の山田正人さんの職場が旧通商産業省、別名、「通常残業省」だったからです。
霞ケ関の官僚にとって、財務省と政治家を説得するのは、重要な仕事です。ところがが、そのどちらも、深夜に呼びつけることなど、なんとも思っていない人種なのです。
「保育園の迎えがあるので退庁させてください」などと言える雰囲気ではありません。
"志の縁結び係"を名乗る私は、2007年5月26日の「福祉と医療・現場と政策の新たなえにしを結ぶ会」で、初対面の2人を引き合わせることを思い立ちました。
以下は大好評だったトークの""超サマリー"です。
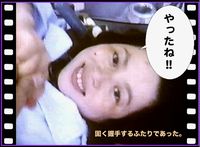
まず春樹さんの話です。
79年4月のある日、ゆみこから「分娩室への招待」を受けました。
ここで、女性との関係、子どもへの考え方、そして、人生観が一変しました。
翌80年の寒い朝、ゆみこがこういいました。
「もううんざりだわ」
−−なにが?
「きょうが燃えないゴミの日だって知ってた? ハテナの保育園のお弁当をもたせなきゃいけない日だと知ってた?」
−−そんなつまらん事をこまごまと知るわけないじゃん!
「そのつまらい事を、誰が毎日やっていると思っているの? 夫や子どものために下働きする一生なんて、ゴメンだわ!」
−−な、何が言いたいんだ?!
「わたしが、働きにでるわ」
−−じゃ、おれはどーなるんだよ?!
「家庭を守ればいーじゃない!」

ショックでした。
男たちが夢や人生の計画を実現させようとしているその陰で、女たちが自分の「夢」や「人生の計画」を捨てている……。そんな社会はよくない。
で、「男の主婦」になっちゃいました。
まわりからは「あなたはフリーだからこういうことができたのよ!」なんていわれて悔しい思いをしたけれど、それは違います。
「こーゆうことをやるためにフリーをやっているんだ」。
こんどは山田さんの話です。
私たち夫婦は、同じ年に、同じ大学の同じ学部を卒業して、同じ通産省に同期で入りました。子どもが生まれる前は夫婦対等でした。
双子が生まれたとき、当然のように妻が育児休業をとりました。私は、相変わらず「24時間働く」ような感じで、妻と私の生活が、全く変わってしまったのです。
そういうときに、3番目の妊娠がわかり、私は無邪気に喜んだんですが、妻はようやく仕事に油がのった時で、「私は産めない」と。

その瞬間、無邪気に喜んでいて仕事ばかりをしていた自分と、家事・育児・仕事で押しつぶされそうになっている妻の間に、大きな川が流れていることに気づきました。そして、決断しました。
育児休業申請書を書いて出したら、上司は、「まさか1年だとは思わなかった」。
男の友人の多くは、育休という言葉さえ知らない。出産の時休むのは「産休」、それが長くなったのが「育休」と思っている。
「山田は産んでもないのに、なんで産休がとれるの?」なんて。
恥ずかしいことですが、育児なんて、それほど頭を使わずにできるんじゃないかと思っていましたが、とんでもない間違いで自分が何もできないと気付きました。
それと、これは、男女問わず辛いと思いますが、仕事から離れるのはすごく辛かった。最初の2〜3カ月は、毎晩仕事の夢を見るんです。
夢のなかでは、パソコンを打ったり生き生きしていて楽しい。
子どもも反応もなかったりするので憂鬱でした。

6カ月を過ぎるころから、育児が本当に日々楽しくなりました。
「ダッコしてー」「絵本よんでー」。
親にとって、子どもに頼られることが、こんなにも幸せなことだとは、育休を取り、子どもと向き合ってみて初めて知りました。
全幅の信頼を私に寄せてくれている子どもたちとの生活を送っている今、私にとって子育ての楽しみは、もはや捨てることはできません。
それぞれのパートナーはいいました。

ゆみこ・ながい・むらせさん:
女と男の関係が変わると家の形も変わります。コの字型のキッチンの両方に流しをもうけ、2人が同時に作業すると、とても、速いんです。
西垣淳子さん:
「俺が育てる。君は仕事をしたら」と彼がいったときには、驚きました。
「どうして3人も育てられるのか」とよく聞かれますが、こう答えています。
「一番頼れるのは自分のパートナー」と。
お母さんに頼っている人多いですが、子育てのパートナーは母じゃなくて夫だと伝えていきたいです。
◇
一人でも多くの男性が、子育ての楽しみ、喜びを味わえる社会になりますように。
P.S.おふたりの往復書簡はこちら。
(大阪ボランティア協会の機関誌『Volo(ウォロ)』6月号より)